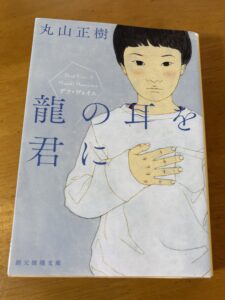
龍がどういう姿形をしているかは知ってるだろう?
龍には、ツノはあるけど耳はない。
龍はツノで音を感知するから、耳が必要なくて退化したんだ。
使われなくなった耳は、とうとう海に落ちてタツノオトシゴになった。
だから、龍には耳がない。
聾という字は、それで「龍の耳」と書くんだよ。(本書より引用)
未知の世界を小説として書くことで、手に取りやすく、ごく自然にその世界に触れられる。理解し寄り添える。
著者として伝えたい思いとの双方を叶えてくれる作品になっているなと思いました。
ろう者や手話の知識だけを一方的に難しく書かれているものは、どうしても読み手も重く捉えがちで、”知識”=”理論”としては理解できても、その世界に寄り添いたいという気持ちとは少し距離を感じてしまいます。
著者自身がコーダなのではないかと思ってしまうくらい、ろう者や手話の知識の豊富さ、表現の仕方、それがとてもリアルで優しくて、扱い方がとても真摯なことに胸を突かれます。
あくまでもこれは小説で、ミステリーでもあります。
でもミステリーのストーリーを面白くするために、決してろう者の世界を作品の題材として都合よく扱ってはいないなと感じました。
著者の熱い真意が伝わってくるあたたかい文章で綴られています。
聴者であってもろう者であっても、誰一人取りこぼすことなく、キャラクタ一の一人一人をとても丁寧に描きながら進んでいくストーリーは胸が熱くなります。
ろう者がろう者だけを騙すという行為は、端からみたら”犯罪”でしかない。
加害者側のろう者だけを狙う真意。
しかし被害者側の「被害届」を出さない被害者側の”そうできない” ”そうしない”思い。
ろう者の世界でしか理解できないこと、聴者には到底想像もできない世界や価値観があるということ。
また、聴覚障がい以外にも「場面緘黙症」(言葉を話したり理解する能力は正常なのに特定の状況では話すことができない)や、発達障害についても扱われています。
この小説では「場面緘黙症」である少年が目撃者となりますが、正しい知識を得られることなく、ただ”子ども” や ”障がい者”というだけで証言を軽視されてしまう現実。
その少年と母親の葛藤や深い繋がりまでも丁寧に綴られていきます。
どの障がいにおいても、それぞれの特性や事情を抱えていることを描きつつ、それに対する社会の偏見を見事に伝えていると思いました。
障がい者に対する世間の目。
警察ですら決めつけや偏見によって事実が歪められてしまう可能性があること。
法の場での手話通訳の実情。知り得なかったルール。
ミステリーというストーリーの中で、スーッと胸がすくような気持ちになりました。
また特別支援学校の教育にも視点が当てられていて、授業の多くは手話で教えるのではないということを知りました。
国語や算数などの授業も手話が使われないということも書いてありました。
(そういう時期があったというだけで現在の教育現場は違っているかもしれません)
「筆談」と「聴覚口話法」で行われるそうです。
「聴覚・聴き取り訓練」
補聴器や人工内耳などを活用して、残存聴力を活用しながら、できる限り多くの音を聞き取る訓練をする。
「口話」
母音は口型を真似して音を出す。
子音は舌がどういう形になるか、動きになるか、口に中を見せて教え、それを真似る。見せるだけではなく、声を出したときの振動なども手を胸が喉に当てたりすることで体験させる。「読話」
口の動きの読み取りを訓練する。
「たばこ」「たまご」「なまこ」といった口の形が同じ単語の区別は困難。
ただこの小説では、手話よりもそこまでして身に付けさせる
「音声言語は本当に大切か?」ということについても語られていました。
果たしてそれは「言葉」なのか、と。
「ことば」
私は日頃から「ことば」を大切に思っています。
それは”音声”だけではなく、”感情”を伴ったものだと。
聴者には聴者の、ろう者にはろう者の、障がい者には障がい者の、
それぞれの「ことば」があります。
だから、お互い同情とかではなく、それぞれの言葉を大切にし、理解し合うことが何より大切なのかな、と私は思います。
それが本当のコミュニケーションの在り方ではないか。
また、そうであってほしいと願ってやみません。
「寄り添う」
大切な、大好きな「ことば」の一つです。


応援お願いします!
気が向いたらポチッとしていただけると励みになります。
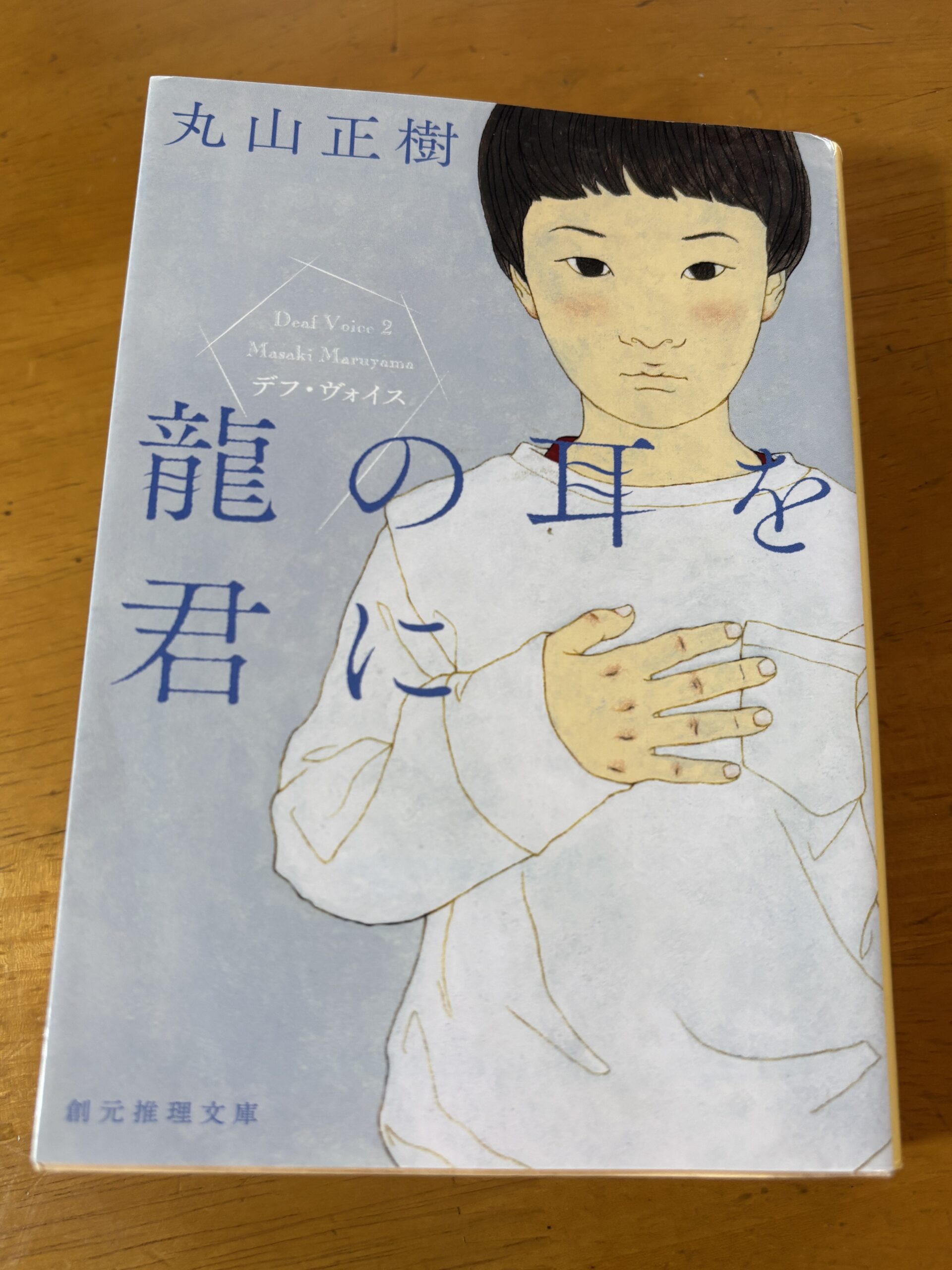

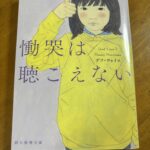
コメント